第46回 食支援は「やるか、やらないか」
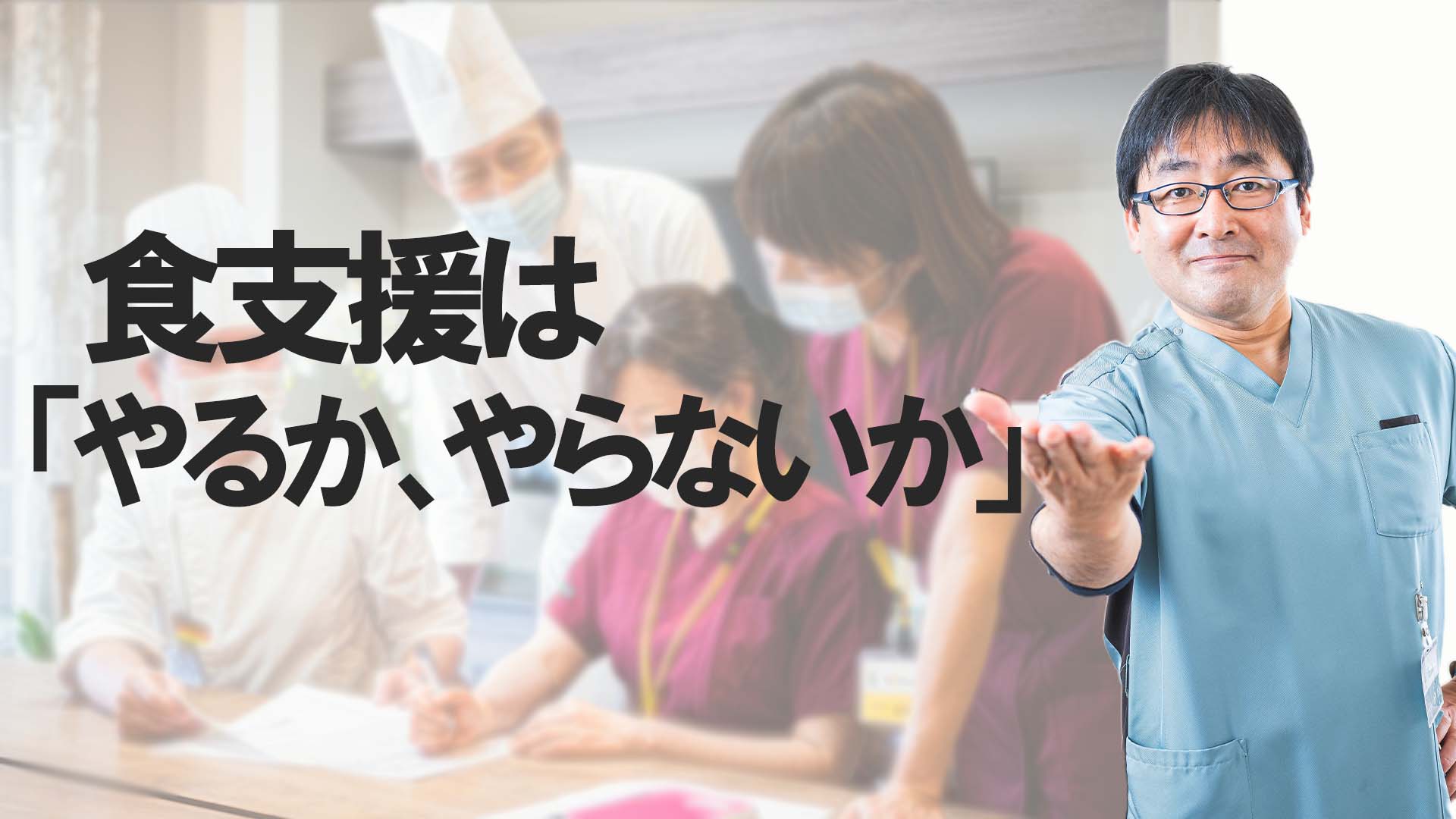
終末期に絶食とせず、亡くなるまで口から食べることを支援する取り組みは「食支援」と呼ばれています。高齢者が誤嚥性肺炎で入院すると、治療 の過程で絶食、 人工栄養となることがあります。 こうした患者は肺炎が治った後も再発予防のため絶食指示が続き、亡くなるまで口から食べられないケースが少なくありません。ですが、再発予防のために患者の「食べる権利」を奪ってもよいのでしょうか?
初診か初診後早い時期に意向を尋ねる
在宅患者の多くは既に食べられないか、もうすぐ食べられなくなる状態にあります。そこで、当院では初診か初診後なるべく早い時期に、患者や家族に「食べられなくなったらどうしたいですか」と質問しています。その際、胃瘻や輸液投与などの人工栄養を行うか、それとも食べられる間は口から食べ、自然に診ていくのかなど、全ての選択肢を提示した上で考えてもらいます。
食べられなくなったらどうしたいかを考えてもらうことは、終末期にどういう医療やケアを受けたいのかを考えてもらうことにつながります。これは、患者や家族、医療従事者などが患者本人の 望む医療・ケアの内容や方針を話し合う「 アドバンス・ ケア・ プランニング(ACP)」そのものといえるでしょう。
その上で、「食べられる間は口から食べ、自然に診ていくこと 」を選んだ患者に対しては食支援を行います。具体的には、口腔ケアや摂食嚥下機能訓練を行い、食べられるようになったら、患者の状態に合った形態の料理を用意します。食べられるようになるまでには、歯科医師や歯科衛生士、 言語聴覚士、管理栄養士、これらの専門職をコー ディネートするケアマネジャーなど多くの専門職が協働することになります。
食支援は「やるか、やらないか」
食支援で最も重要なのは、患者の食べる意欲を引き出すことです。実は、人工栄養が患者の食べる意欲を阻害していることが多く、人工栄養を止めたり減らしたりすると、患者は空腹を感じ、食べる意欲が回復します。経験上、食べたいものを大きな声で言える患者は食べられることが多く、これを勝手に「永井の法則」と呼んでいます。
たんぽぽクリニックではこれまで 100 例近い食支援を行ってきました。その経験から、食べる意欲があって唾液や喀痰の吸引が必要なければ積極的に経口摂取を進め、食べる意欲がなく人工栄養を行っている患者については人工栄養の減量や一旦中止を試みて、食べる意欲がわけば経口摂取を進めるようにしています。
今でこそ当院には食支援に必要な専門職が在籍していますが、食支援という言葉もない頃から医師と看護師だけでできる支援を行ってきました。地域に連携できる専門職がいれば連携して取り組んでほしいですが、やる気になれば医師と看護師だけでも不可能ではありません。
食支援は「できるか、できないか」ではなく、「やるか、やらないか」なのです。
地域には必ず、食支援を必要とする患者がいます。その潜在ニーズに応えることが、地域の在宅医療のニーズを掘り起こすことにもつながります。
関連動画 食支援は「やるか、やらないか」