第46回 「終末期に点滴をしないこと」を納得してもらうために
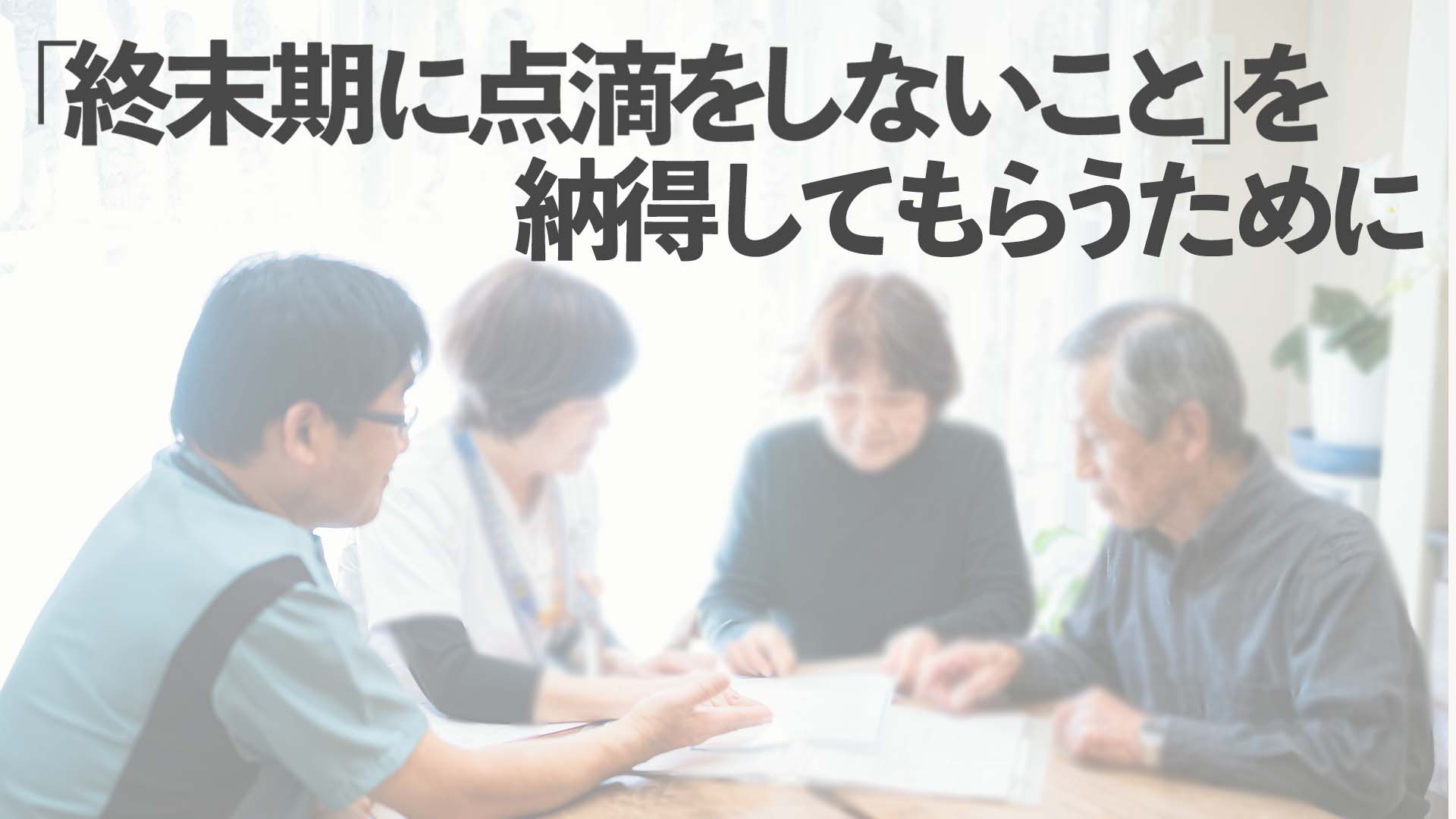
穏やかな死への過程
老衰や病気で死期が近づくと、口から食べたり飲んだりすることができなくなります。結果としてゆっくりと脱水状態になりますが、この脱水には、麻薬のような鎮静効果があります。脱水が進むと、徐々に眠る時間が増え(日中も眠っている状態=傾眠)、日常生活動作(ADL)も低下していきますが、本人にとってはとても穏やかで楽な状態なのです。
人間の終末期の体の変化は、誕生後の成長過程を逆にたどるようなものと考えるとわかりやすいかもしれません。生まれたばかりの赤ちゃんは寝返りすら打てず、介護保険でいえば要介護5の状態です。そこから次第に食事量が増え、起きている時間が長くなり、動けるようになります。つまり、成長にともない介護度は下がっていくわけです。
終末期はその逆です。亡くなる前に食べられなくなるのは、身体のすべての機能が低下し、水分さえ体内でうまく処理できなくなるからです。このような状態で水分や栄養を無理に入れると、体外に排出できず、むくみや腹水、痰・唾液の増加などを招き、かえって患者さんを苦しめてしまうことになります。
「枯れるように亡くなる」という表現がありますが、これは余計な水分で体をむくませることなく、草木が静かに枯れていくように、自然のままに息を引き取る状態のことだと思います。
ですから私は、「身体で水分を処理できなくなったら、あえて脱水状態に近づけて自然に看ていくことが、最期を穏やかに過ごすための方法です」と説明しています。死は病気ではありません。身体の状態に応じた傾眠、ADL、食事量が整えば、呼吸も穏やかになり、安らかな最期を迎えることができるのです。
終末期の点滴の悪循環
しかし、日本の多くの病院では、終末期であっても亡くなるまで点滴を続けています。その結果、体内で処理できない水分により体がパンパンにむくみ、唾液や痰が増えて喀痰吸引が必要になります。誤嚥性肺炎を防ぐために絶食指示が出され、摂食・嚥下機能はさらに低下します。
点滴や喀痰吸引といった医療処置が24時間必要になると、「もう自宅では看られない」と医師も家族も考えるようになり、結果として患者は自宅に戻れず、病院で最期を迎えることになるのです。これが終末期の点滴の悪循環です。この悪循環が続く限り、自宅での看取りは広がっていかないと私は考えています。
在宅医療や看取りをテーマにした私の講演でもこの話をしますが、参加した医師からは「点滴をしない方がよいとわかっていても、家族が希望するから中止できない」とよく言われます。
もちろん、一人ひとりにとっての最善は異なります。つらく苦しい治療であっても、それによって1分1秒でも長く生きることを望む人もいます。しかし、終末期に点滴を希望するご家族の多くは、「点滴をしない=何も手を尽くしていない」「見殺しにするようで耐えられない」という思い込みを抱えているのです。
だからこそ、このような誤解を解き、納得してもらえるための「説明の技量」が、在宅医療に携わる医師やスタッフに強く求められているのです。
説得の壁を超えるために
終末期に点滴をしない方が患者さんが楽に過ごせるということは、看取りの経験がある医師や看護師なら体感的にわかっていることです。しかし、実際の現場でそれを実践するのは簡単ではありません。私自身もかつてはそうでした。
現在、たんぽぽクリニックの診療でも、終末期の患者さんに対して「どのように輸液量を絞っていくか」は、常にミーティングの議題になります。どのように説明すれば、患者さんやご家族に納得してもらえるのか。私は、次の4つのポイントを大切にしています。
納得してもらうための説明:4つのポイント
ポイント1:死に向き合うこと
家族、そして意識がしっかりしている場合は患者本人にも、「限られた命である」という現実を伝えること。「食べられないから死ぬ」のではなく、「死が近づいているから食べられなくなる」のだと理解してもらいます。その前提が共有されていない限り、説明は平行線をたどってしまいます。まずは医療者自身が、患者の死に向き合う姿勢を持つことが大切です。
ポイント2:水分の処理ができない状態であることを伝える
終末期の身体では腎機能などが低下し、水分の処理が難しくなります。点滴をしても排出できず、体内に溜まることで、むくみ・痰・唾液の増加を招き、呼吸困難や吸引の必要性が生じてしまいます。点滴を控えた方が、結果として本人の身体はずっと楽なのだということを丁寧に伝えることが大切です。
ポイント3:最期は本人が楽に過ごすことを優先する
ご家族は当然、できるだけ長く生きてほしいと願います。しかし、点滴が逆に本人を苦しめてしまうのなら、それは本末転倒です。「最期を楽に過ごしてもらう」という目標をしっかり確認し、ご家族や関係する多職種と共有しましょう。
ポイント4:最期まで"食べること"を支援する
点滴を行わなければ、痰や唾液が増えにくく、吸引が不要になることが多いです。つまり、唾液を飲み込める程度の機能は残っているのです。患者さんが食べたいものを、食べられる形に工夫して提供し、口から少しでも摂ることで、ご本人もご家族も大きな満足感を得ることができます。
もちろん、点滴をしないこと自体が目的ではありません。点滴という選択肢も提示しながら、上記の4つのポイントを丁寧に説明すれば、多くの患者さん・ご家族は自然で穏やかな最期を選ばれます。
それでもどうしても点滴を希望される場合には、症状が出ないように輸液量を調整しながら慎重に開始し、徐々に減量して最終的には200ml以下に抑えます。これくらいの量であれば、むくみや痰の増加もほとんど見られず、吸引の必要もなく、患者さんへの負担も軽減されます。
家族の思いも大切にしながら、しかし患者さん自身が苦しまないように――。そのバランスを見極めながら、どんな選択になっても、私たち医療・介護に携わる専門職は、ご家族とともに悩み、寄り添いながら支えていく姿勢が何より大切だと考えています。