第27回 在宅医療の鍵は退院困難者への対応
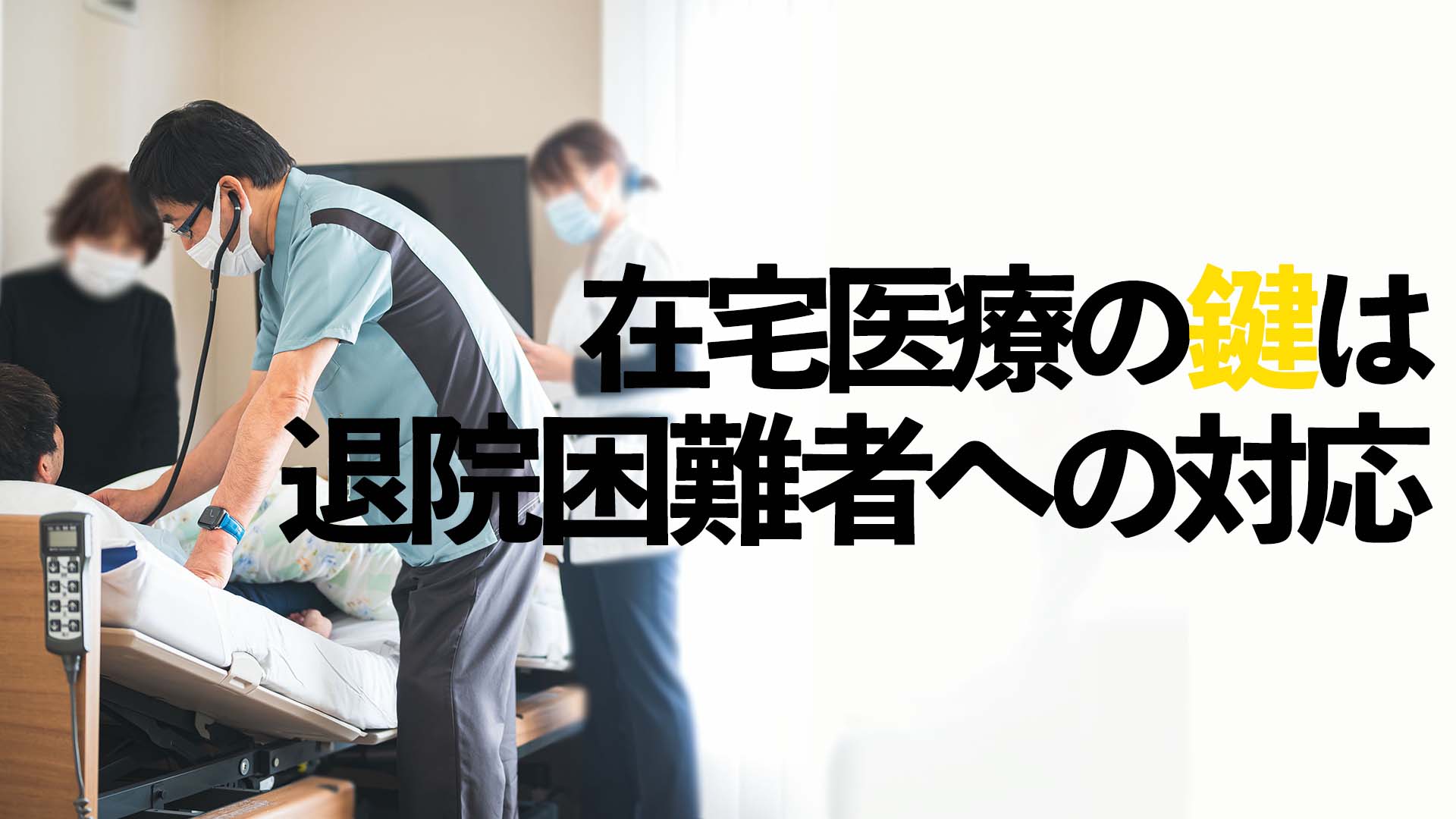
みなさんはご覧になったでしょうか?厚生労働省から令和6年8月26日に、「新たな地域医療構想を通じて目指すべき医療について」という資料が出されています。
今後の在宅医療、地域医療構想を出していく中で、どのような医療、特に在宅医療が求められていくのかというのを厚生労働省が示していました。
その中で、今後も高齢者はどんどん増えて、死亡者も増え、在宅医療のニーズは非常にあるという見解を出した上で、今後の在宅医療のポイントとして、「退院困難者への対応」であると書いています。入退院支援加算の対象者における退院困難な要因で、そのポイントになるのは、病院から在宅に帰っていく、 急性期病院から回復期病棟や地域包括ケア病棟などを通じて在宅に帰っていくときに、入院前に比べてADLが低下して、退院後の生活様式の再編が必要である人です。そこをどうしていけるかが、非常に大切だと書いていました。
実際その通りだと思います。例えば肺炎で入院して、今まで通り口から取れなくなった人が家に帰るときに、人工栄養や吸引が必要になった、ADLが急激に下がって寝たきりになった、今まで家族が介護していたけれども介護できなくなったり、いろんなサービスを導入していたけれども、さらにたくさんのサービスが必要になって、在宅で介護するのが難しくなったりなど、そういう人もたくさんいるわけです。そういう人たちを、それまで診療していた先生がそのまま在宅でも診療できるというのであれば、その先生が続けて診るわけですけれども、診ることができなくなるわけです。昔は、本当に軽い患者さんだけを診る在宅医療が行われていたわけですが、今ではどんな重度の患者でも、最期は看取りまでしっかり診ていける在宅医療が求められると思います。
入院してADLが低下したり、医療処置が増えたり、重度化したときでも在宅で診れる、そのような在宅のクリニックや訪問看護ステーション、多職種のチームが地域の中に必要とされているわけです。
そういう状況になったときも、昔はずっと病院で見ていたわけです。病院がいい人もいれば、家に帰りたい人もいるし、家で過ごしたい人もいるわけですから、そういう人をしっかりと家で診れるような体制をとっていくことが大事ですし、そこができなければ病院から在宅患者の紹介もされないわけです。国としてもそのような重度患者を病院でずっと診ていくのではなくて、もちろん介護施設や老人ホームなど、施設に入るという選択肢もありますし、家に帰ることを希望される人は家で診れる体制づくりが必要になります。
そして、私たちにとっては、この退院困難な状況、状況が変わって重度化して退院が困難になった人をいかに診ていけるかが非常にポイントになると思いますし、この国の考えも正しいと思って、私たちはそこを目指していきたいと思っています。
そして困難事例のほとんどは正当な要求をされている人の方がむしろ多いと私は思っていますが、困難事例でも断ることなく診ていける、そういう在宅のチーム作りが地域の中でもっともっと重要になっていくと思うので、「退院時に在宅が困難な状態の人をいかに診ていけるか」というのを私たちもテーマとして今後も大切に関わっていきたいと思っています。