第26回 全職員で全体ミーティングやっていますか?
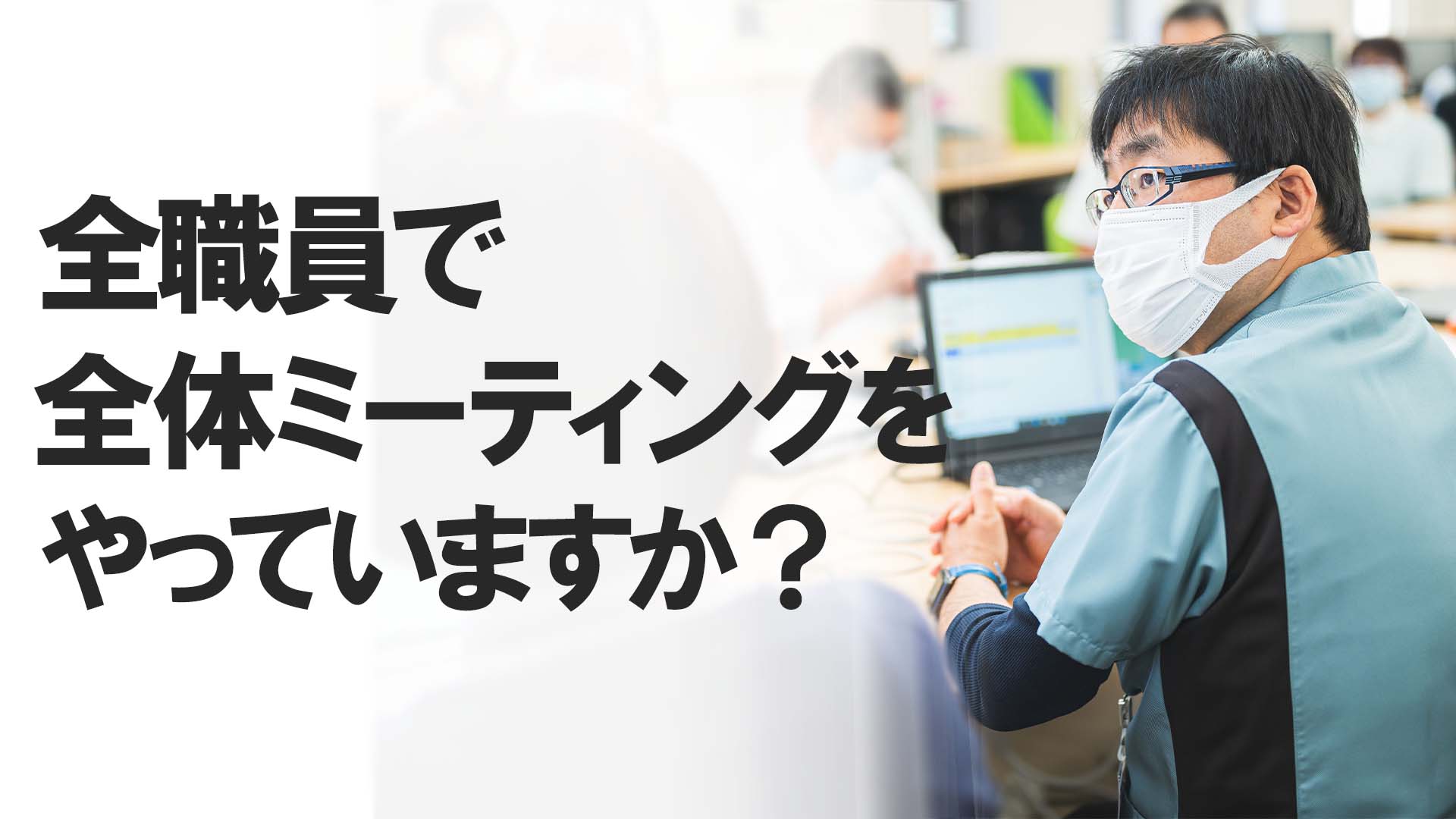
患者数の増加に対応するため、複数医師体制を構築し、職員数を増加させていくことは、医師や看護師が疲弊しないためには重要な取り組みです。しかし医師や職員数が増加していくと、対応の質にばらつきが生じ、クリニックとして目指していた理念と離れていく問題が生じるようになります。全国の大規模で有名な在宅クリニックでも、効率化を重視するあまりミーティングをあまり行っていないところも多く存在しているようです。当院が開業以来ずっと大切にしている朝の全体ミーティングについてお話ししたいと思います。
当院は開業以来、始業時に全職員が参加する全体ミーティングを実施しています。松山市にあるたんぽぽクリニックから100km離れたへき地診療所もオンラインでつなぎ、合同で行っています。全職員が参加する朝の全体ミーティングは30分ほど毎日行っており、その後部署別にミーティングを実施しています。チームで対応するためには情報の共有と方針の統一が何よりも重要だと思うのです。情報共有は電子カルテや情報共有ツールを使って行いますが、方針の統一を図るためには、直接の議論が欠かせません。全体ミーティングでは情報共有のための報告だけに終始せず、要点のみを発言し、その状況や対応方法についての議論に時間を割くようにしています。
特に看取り段階の患者については、細心の注意が必要です。患者の疼痛コントロールや訪問頻度、残された時間でその人らしい時間を過ごすための支援方法について詳細に議論を行います。このような議論を通じて、全職員が一丸となって患者とその家族を支える体制を整えることができると思うのです。
理念の共有と職員の教育・研修機能
毎朝、患者・家族とどう向き合い、1例1例にどのように対応するかを議論することで、医師や看護師、多職種のスタッフ、事務職員まで当院の理念を学ぶ貴重な時間となっています。事務職員もたんぽぽクリニックの理念を深く理解し、日々の来客対応や電話対応を行えるようになっています。また、当院には、将来在宅医療の開業を目指す若手医師や研修医も多く在籍しています。朝の全体ミーティングでの議論を通じて、在宅医療のエッセンスを学び、質の高い在宅医療を提供するための教育研修機能としても重要な役割を果たしています。また、全国から当院を見学する方も多く、この全体ミーティングで見学者の活動や取り組みを発表してもらうことで、私たちも学ぶ機会となっています。
理念の共有を徹底することで、全職員が一丸となり同じ目標に向かって取り組むことができます。これにより、患者や家族への対応が一貫性を持ち、質の高い医療サービスを提供できるようになるのです。理念の共有は、単に理念を知るだけでなく、日々の業務にどのように反映させるかを考えることが重要となります。
また、週1回全体ミーティング開始前に当法人のクレドを唱和し、職員一人ひとりのエピソードを話す時間を作ることで理念の共有を深めています。クレドの唱和は、日々の業務に対する姿勢や心構えを再確認する機会となり、全職員が同じ目標に向かって働くための基盤を作ります。エピソードの共有は、職員同士の理解を深め、職場の一体感を高める効果があると考えています。
多職種で参加する意義
朝の全体ミーティングには、多職種が参加することが重要です。在宅医療の質を向上させるためには、医療だけでなく生活を支え、患者やその家族が自分らしい人生を送るための支援が不可欠です。当院では、リハビリ職、ケアマネジャー、鍼灸マッサージ師、医療ソーシャルワーカー、管理栄養士、ヘルパーなど多職種が全体ミーティングに参加し、多方面から患者・家族にとって最善の方法を議論し取り組んでいます。連携している外部の調剤薬局の薬剤師も定期的に参加しており、職種を超えて患者・家族にどう関わるかを議論する場が全体ミーティングの時間となっています。
多職種の参加によって、異なる視点から患者のケアを考えることができます。例えば、リハビリ職からの視点では、患者の日常生活動作の改善や維持、患者が叶えたいことについての具体的なアプローチが提案されます。ケアマネジャーからは、在宅介護サービスの利用方法や支援体制についての情報提供が行われます。鍼灸マッサージ師からは、疼痛管理やリラクゼーションの方法についての助言が得られます。医療ソーシャルワーカーからは、患者や家族が抱える社会的な問題や経済的な支援についての提案があり、管理栄養士からは、栄養管理や食事指導についてのアドバイスが提供されます。これら多職種の視点を取り入れることで、患者一人ひとりに対してより総合的で個別化されたケアが提供できるようになります。また、多職種間の連携が深まることで、情報の共有や業務の効率化が図られ、チーム全体としてのパフォーマンスが向上するのです。
コミュニケーションの強化
ミーティングは、部門間や職種間のコミュニケーションを強化し、協力を促進する重要な場でもあります。顔を合わせたやり取りを通じて、日々の業務で発生する問題や課題の解決策を迅速に考えることができるのです。コミュニケーションの強化により、職員同士の信頼関係も深まります。信頼関係が構築されることで、職員間の協力がスムーズになり、業務の効率化が図られます。また、良好なコミュニケーションは職場の雰囲気を良くし、職員のモチベーション向上にもつながります。顔を合わせて話し合う時間が、職員一人ひとりの意識を高め、組織全体の力を引き出す原動力となると思います。
全体ミーティングを実施する際のポイント
多職種が参加するため、できるだけ専門用語を避け、分かりやすい用語を使うことが重要です。医師だけが理解できる専門用語では議論が成り立ちません。また、朝の始まりとして全職員の意識を整えるため、「朝の挨拶」を大切にしています。「今日もたくさんの患者様・利用者様・ご家族様が私たちの訪問を楽しみに待っています。今日も1日笑顔でよろしくお願いします」といった言葉で一日がスタートするのです。
また、全体ミーティングでは、議論が白熱して長引くことがありますが、時間管理も重要です。ミーティングの進行役は、時間を意識しつつ、さまざまな職員が発言できるように配慮する必要があります。
全体ミーティングは、情報共有と方針の統一、コミュニケーションの強化、職員の教育・研修、多職種間の連携、理念の共有など、さまざまな目的を持って実施します。これらの目的を達成するためには、ミーティングの進行方法や内容、参加者の意識が重要です。全職員が一丸となって、質の高い在宅医療を提供するために、全体ミーティングを効果的に活用していきたいものです。