第8回 未来の在宅医療は薄利多売の在宅医療!?
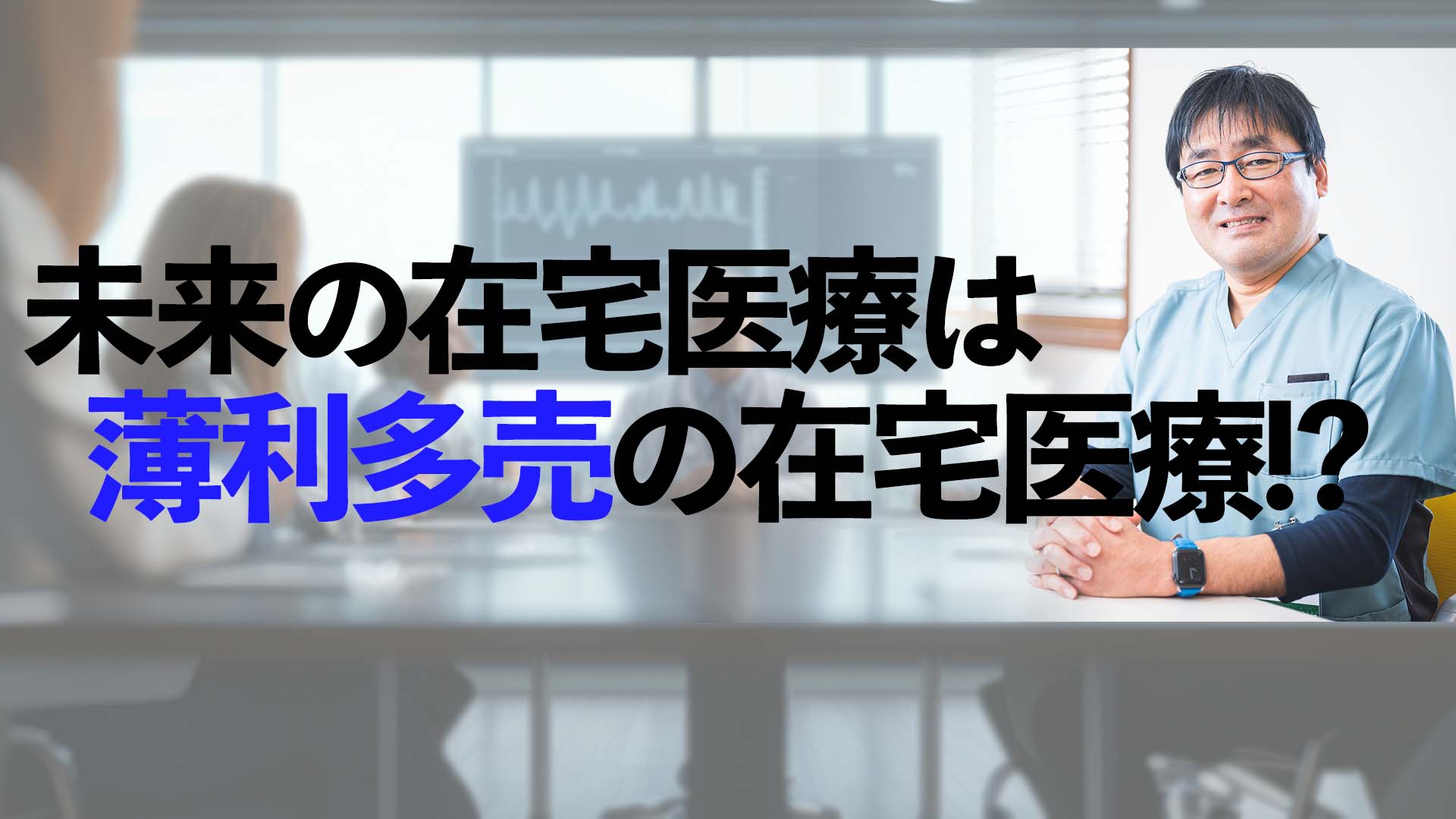
先日、「クリニックばんぶう」(日本医療企画)という医療系の雑誌で、「パイオニアたちが描く在宅医療の未来戦略」という特集に私の記事も掲載されました。私は、「患者の希望の実現を重視し選ばれる診療所を作る」というお話をしました。
今後、さらに高齢化が進んで在宅医療のニーズ自体は非常に高まると思います。厚生労働省もそのように試算していますし、私たちもそう認識していますので、今後、この在宅医療のニーズは増えていくけれども、どのようになっていくのだろうと考えています。
2025年問題、団塊の世代が後期高齢者になって、死亡者も非常に多くなるという時代になってきていますし、求められる在宅医療も増えていくと言われています。
この特集で、私はその将来のニーズに向けて在宅医療の質を高める話をしたのですが、他の記事には、何人かの先生が、未来の在宅医療のニーズは確かに増えるけれども、薄利多売の在宅医療になると書いていました。その記事を読んで、「薄利多売の在宅医療」というのはどうかと思ったわけです。
都会の方には、在宅医療のクリニックが結構たくさんできているのですが、「看取り数を増やす」「診療の患者を増やす」というのを目的にして、民間の事業者の方が経営し、医者をたくさん集めているという話をよく聞きます。非常に高い何千万円もの年収を出して、「とにかく数を見てくれ、聴診器も当てなくていいし、午後から最低30人以上見てくれ」などと指示されるそうです。患者さんの数をたくさん見ることを目的にしているわけです。
もちろん行っているのは診療だけです。地域の多職種の連携というのはあまり重視されずに、診療だけ行っているのです。その理由は、診療が一番効率よく大きい収入を得られるからです。診療以外の多職種のチームを作ったりすると、経営的には厳しいので、とにかく診療の数をたくさん見て、質を度外視して、その代わり非常に高い年収を医師に支給するというクリニックが結構増えてきているようです。都会の方でしっかり良い在宅医療をしている先生たちももちろんたくさんいるのですが、そういう先生方からも、これでいいのだろうかという話を時々聞きます。そういう意味で、本当に薄利多売の在宅医療が当たり前の時代になった時には、在宅医療自体が、どうなのかと思われるようになっていくと思います。
一人一人の患者さんにとって、療養生活や在宅医療のゴールである看取りは、一人一回だけなので、その一回だけの療養や看取りを、ただ数だけをこなす医療者に見てもらうとなると本当に寂しいものになると思うのです。
だから、医療は医者のためにあるわけではもちろんないし、その患者さんにとって最善の療養生活や看取りを行うことができるようにいかに質を高めていけるか、望む最期を迎える、望むところで最期を迎えることを目指して、様々な多職種のチームでしっかり生活を支えて、家で療養したい人、家で看取りをしたい人は、安心して生活や介護ができるように、そのサポートをしていきたいと思っています。
最期は絶食ではなくて、しっかり食支援をして、医療を最小限にすることで本人が食べたいものを最後まで食べることができるようにしたいですし、やりたいことを支援したいと思っています。医療だけではないと思うのです。医者だけではなくて、多職種のチームでしっかり生活を支えて、家で療養をしたい人、家で看取りをしたい人を、チームで実現していく、そういう在宅医療を質を高めて提供できればと思っています。それを目指すような医療機関がどんどん増えていくようにしなければいけないとも思います。それは先に取り組みをしてきた者としての使命なので、未来の在宅医療はより質の高い在宅医療となるようこれからも頑張っていきたいと思います。
関連動画 未来の在宅医療は薄利多売の在宅医療!?